聴覚過敏自体は病気ではなく、ストレスなどによる症状の一種です。
いわば耳鳴りのようなものですね。

耳鳴りと同様に、ストレスから来るものもあれば生活習慣から来るものもあります。
聴覚過敏は耳鳴り同様にそれ自体が病気なわけではありません。
そのため、これといった治療法はなく、原因となっている要因を改善してあげる必要があり、聴覚過敏の治療は時間がかかってしまいます。
当然ストレスは増え、それが悪循環となってますますひどくなるといったことも考えられます。
イヤーマフを付けるなどの対策をして、なるべく不快な音を聞かないようにしてゆっくり原因を改善していきましょう。
聴覚過敏の症状
聴覚過敏という字面から症状を想像すると、ものすごい小さい音が聞き取れるようになるというような印象を受けるこの症状。
実際はどのような症状なのでしょうか。
どんな些細な音も聞き取れる野性動物のようになれるかというとそういうことではありません。
通常よりも音が響くという症状になりますが、響くと言われてもよくわかりませんよね。
響くというのは、脳が揺れるような音に聞こえたり、耳に刺さるような音に聞こえるということになります。
これにより、頭痛や耳が痛くなってしまいます。
聴覚過敏で不快な音

聴覚過敏で特に不快な音が
- 人の話し声
- 子供の声
- 緊急車両のサイレン
- ノック
- 食器の音
など低音よりも高音の方が不快に感じる事が多いです。
また、突発的な音も苦手としています。
これは体調などによっても変わります。
聴覚過敏のメカニズム

音が聞こえづらくなるのはある程度理解できると思いますが、過敏になってしまうのはなぜなのでしょう。
音を伝える機能が正常に働いていない
耳は、音を大きくするだけではなく小さく調整することもできます。
意識して目の前の人の話を聞こうとすると、その周りの人の声が気にならなくなったりしますよね。
このような、音の大小の調整をしている機能がうまく働いていないと、音が響いてしまうことがあります。
顔面の神経麻痺やてんかんなどではこの機能がうまく働かずに聴覚過敏の症状がでることがあります。
脳機能の障害
人間は音を耳ではなく、脳で聞いています。
というと「はぁ?」と思うかもしれませんね。
耳はあくまでも音を集める機関で、いわばマイクのようなものです。
その耳で集めた音を電気信号に変えて、脳で音として認識します。
その中で人間は音の取捨選択ができます。
要らない音はミュートし、聞きたい音は大きくすることができるのです。
脳になんらかの障害がありこれができないと、脳はすべての音をしっかり聞こうとしてしまいます。
これにより聴覚過敏が引き起こされていることがあります。
また、脳が音を認識している聴覚野の感度が上がっているケースもあります。
頭痛がある場合は、このように聴覚野の感度が上がっている可能性があります。
自律神経の乱れ
自律神経の乱れでも聴覚過敏を引き起こすことがあります。
交感神経が常に優位だと、アドレナリンが分泌され、緊張状態となります。
これにより、血管の収縮などが過度に起こり、聴覚過敏や耳鳴りなどの耳の不調に繋がります。
対処法
残念ながら聴覚過敏には厳密な治療方法はありません。
色々な原因が考えられるので、これをやっておけば治る!ということが言えないんですね。
応急的な対応としてイヤーマフや耳栓をつけて、外の音自体を小さくするという方法があります。
また根本的な原因を治す方法として、姿勢を正す、漢方などで体質を改善するといった方法で自律神経の乱れを整える方法があります。
漢方での体質改善を漢方で体質改善をして耳鳴りや聴覚過敏を治す方法という記事で、姿勢やストレートネックに関しては耳鳴りの原因は体の歪み? 体の歪みが耳に与える影響や頭痛や耳鳴りなど様々の症状の原因 ストレートネックとはという記事で紹介しています。
聴覚過敏も原因は耳鳴りと同じようなものが多いため、是非参考にしてください。
まとめ
このように、聴覚過敏とひとえにいってもその原因は様々です。
原因の特定は古人ではなかなか難しいので、いつもよりも高い音などが耳に痛いと感じたりする場合は、是非病院を受診してください。
聴覚過敏は病気ではなく、あくまでも症状の1つです。
体からの不調のサインなので、必ず病院にいき診察を受けましょう。
これを期に食生活の見直しや、適度な運動など自身の健康について考えてみてください。
その体の不調が、耳鳴りや難聴の原因となるかもしれません。
その他聴覚に関する症状

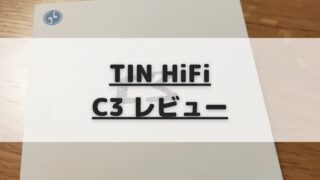


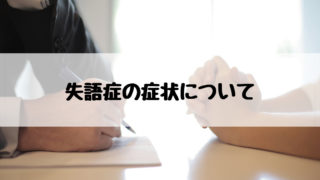



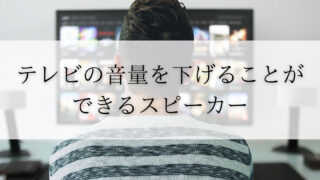





コメント